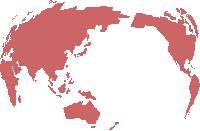
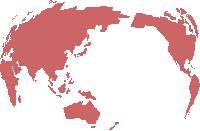
目次
![]() 科学理論の真偽の問題(卒業研究、1974年3月)
科学理論の真偽の問題(卒業研究、1974年3月)
本文
謝辞・出典・参考文献
![]() あとがきに代えて(2007/11/18更新)
あとがきに代えて(2007/11/18更新)
1. 私の学生時代
2. 学説や意見の真偽について
3. 理論の道具的利用
科学理論の真偽の問題 堀場康一 科学理論の真偽に関する問題、すなわち、ある理論が真であるか それとも偽であるか、という問題は長い間論議の的となっている。 そこで、さまざまな認識論上の立場からこの問題をながめていくこ とにしよう。 まず最初に考えられるのは、理論のなかの各命題の真偽が直接観 察によって検証できるかどうか、ということであろう。しかしなが ら、法則をあらわしているような命題の場合、その対象領域が無限 個の個体から成立しているときには検証が不可能であるから、一般 には直接に各命題の真偽を確かめることはできないといえる。 そこでつぎに理論を論理的に整理することを考えてみよう。そう すると理論は、一階の述語論理にもとづく形式的体系である集合論 のなかに書き込むことができる(例としてZFの公理的集合論、シ ュピス・マッキンゼーの力学の公理系)。このような形に整理され た理論のモデルを考えることにすれば、タルスキー以来のモデル理 論のやり方で、モデルについての真偽を定義できる。 しかし、ゲーデルの不完全性定理や、あるいは最近の集合論の諸 公理の独立性の証明により明らかなように、このような整理を受け た理論には複数のモデルが存在する。そして、これら複数のモデル のうちのどれが「真」のモデルであるかを決定するには、もはや上 に述べたモデル理論の方法は使えない。それゆえに、理論のなかの 命題の真偽も、理論のモデルについての真偽も、直接には検証でき ない。 一方、論理実証主義者は、理論の命題をすべて観察可能な命題 (現象主義的な感覚−内容をあらわす言語もしくは物理主義的な物 言語、を用いた命題)に翻訳しようと試み、そして、このような観 察可能な命題への翻訳可能性を真偽に関する有意味性の基準にすべ きだと主張した。けれど、実際にはこれらの翻訳は不可能であり、 従って翻訳可能性を真偽の判定の基準にするのは不適当であるとい える。 以上のことから、理論のすべての命題の真偽を一義的に確定でき るとする考え方は、むしろ捨てた方がよいのではなかろうか。そし て、理論は道具的な機能──我々の経験資料を組織だて、実験法則 を整理するための、技術的な指導原理としての役割──をはたすも のと考えた方が現実的であれ、実際的であると思われる。 周知のように、ニュートンの力学理論は、惑星の運行や物体の自 由落下、潮の干満に関する法則ばかりでなく、液体や気体の浮力、 気体の熱的性質を扱う法則を説明するのにも役立っている。そして、 現代の量子論は、その定式化をさまざまに解釈することにより、広 い領域の物理的化学的現象に体系的な説明を与えている。また、理 論のなかの命題の一部を対応規則を用いて観察や実験の具体的事実 と関係づけることにより、これから生起する事象や過程を予測する ことも可能である。 とはいえ、理論の道具的機能を充分に認識することは、理論の真 偽の問題を相対的に論ずることの論理的妥当性を認めることと矛盾 しない。つまり、個々のモデルについて理論の真偽を問うことは有 意義である。 (1974年3月発表) |
| 謝辞 本稿の作成にあたり、東京工業大学の当時の指導教官、森雄次先生および吉田夏彦先生に大変お世話になりました。この場をかりて、心から謝意を表します。 出典 「昭和48年度 化学科卒業研究論文発表会講演要旨」東京工業大学理学部化学科、昭和49年(1974年)3月9日。 参考文献 Elliott Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, Van Nostrand, 1964. Ernest Nagel, The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation, Harcourt, Brace & World, 1961. Partick Suppes, Introduction to Logic, Van Nostrand, 1957. Gaisi Takeuti and Wilson M. Zaring, Introduction to Axiomatic Set Theory, Springer-Verlag, 1971. |
■ あとがきに代えて
1. 私の学生時代
学生時代に学んだことが多くの点で自分の考え方や行動の基礎になっていると近頃折に触れて思うようになった。どんなに学生時代から遠ざかろうと、当時の出来事が自分の胸のなかに刻まれ、渦巻いているような気がする。
私が大学(東京工業大学)に在籍していたのは、全国各地の大学が大きく揺れ動いた1970年前後だった。大学に入学してまもなく全学封鎖となり、半年近く授業がなかったので、ヨットの部活やアルバイトなどで授業の空白をやり過ごすことが多かった。
専攻は最初数学科で二年間学んだが、その後化学科に転籍して再出発し、卒業することができた。数学では、主として抽象的な思考を手がかりに問題を解いていく。これに対し化学では、ある課題が与えられると、一般に実験を行い、実験結果を確認し検証しながら、問題解決に取り組む。抽象的思考の数学に対し、具体的思考の化学といってよいかもしれない。
化学といっても範囲は広く、有機化学・無機化学・分析化学・物理化学・生物化学などの分野が含まれる。化学の授業では、頻繁に実験実習があり、いつも実験レポートをまとめるのに頭をひねった。日常的に実験器具や装置を取り扱い操作して、多種多様な化学実験をやらせてもらったことは、頭が空回りするのを防ぐと共に、具体的事象をきちんと見る経験を積むことができた。
卒業研究は哲学の吉田夏彦先生のご指導を仰ぎ、科学哲学(科学と哲学の関係)を学んだ。哲学や数理論理学の予備知識が限られていたので悪戦苦闘したが、どうにか卒業できたのは恩師 吉田夏彦先生のご指導ご鞭撻の賜物である。と同時に、科学哲学分野の卒研選択を承諾して下さった、森雄次先生はじめ化学科の先生方に感謝の気持ちで一杯である。
2. 学説や意見の真偽について
私たちのまわりを見回すと、政治・経済はじめ様々な分野で、連日議論が戦わされている。そして専門家、学識経験者、政治家、経営者、評論家、コメンテーター等の人たちが、さまざまに自説を唱え、主張している。
そのような議論は結構なことであるが、その際心に留めておいた方がよいことがある。すなわち、
「いかなる議論であれ、各人の“学説や意見”を“理論”の形にきちんと整理した場合、その理論自体の真偽を一義的に確定することはできない。」
ということである。
ここでいう理論には、自然科学や工学の理論はもとより、心理学・経済学・政治学などの人文・社会科学の理論も当てはまる。この点が私の卒業研究の中心テーマになっている。
3. 理論の道具的利用
ところで、理論の真偽が一義的に確定できないからといって、理論がすべて無駄になるわけではない。
理論の相対的な整合性や妥当性を論じ合ったり、あるいは、理論を現実の事象や出来事に適用した場合の有効性、いいかえれば、どのていど有効にその事象や出来事を説明できるかを議論するのは、理論の改良および発展に役立つ。
そして、そのような理論の改良および発展を通じ、私たちを取り巻く現実社会に何らかの貢献をすることは可能である。
以上のようなことから、理論を無視したり、あるいは理論の真偽にいたずらに固執するのでなく、理論の整合性を吟味しつつ、理論を道具(ツール)として有効に活用しようというのが、私たちの立場であり、目ざすところである。(堀場康一 記)
(Ver. 1.21 2009/11/19)
Copyright (c) Koichi Horiba, 1974-2009